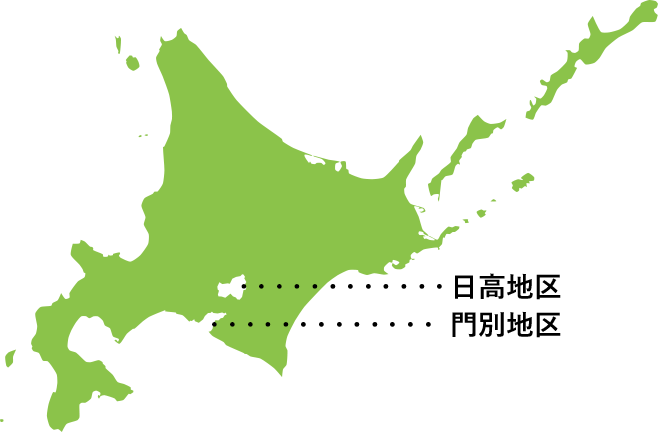(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
メニュー
「町長日記」(令和5年度)
- 掲載日
- 2024年3月27日更新
そろって全国大会へ
令和6年3月27日(水曜日)
小学生の「多賀グリーンカップ争奪第20回学童軟式野球3年生大会」と中学生の「日本リトルシニア全国選抜野球大会」にそれぞれ富川小学校と富川中学校から出場することになりました。

まず小学生は、富川小学校3年生の田村陽輝君と白石瑛太郎君です。2人とも町内の野球少年団JBC日高ブレイブに所属していますが、1月に歌志内市で101人が参加して行われた北海道選抜チーム(2チーム)の選考会に挑戦して、見事36人のメンバーに選ばれました。大会は、全国から小学校3年生で編成する32チームが参加して3月30日から滋賀県で開催されるとのことですが、2人とも「全国大会は初めてだけど、大きな舞台で自分の力を出し切り優勝します」と力強く話していました。ちなみに、白石君は昨年、阪神にドラフト2位で入団し、今シ-ズンの活躍が期待されている門別啓人投手のいとこだそうです。
中学生は、JBC日高ブレイブの出身で、現在は硬式野球チーム苫小牧リトルシニアに所属している富川中学校2年の伊藤颯佑君と同校1年の佐藤来覇君です。このチームは昨年10月行われた秋季の全道大会新人戦で5位となり、全国大会への出場権を獲得しました。全国大会は3月25日から64チームが参加して開催され、2人とも「初めての全国大会で緊張するけれど一つでも多く勝ちたい」と言っていましたが、伊藤君はキャッチャーで3番か4番を打つ主力選手、佐藤君もサードでレギュラーとのことで活躍が期待されます。

田村君、白石君、伊藤君、佐藤君、それぞれに普段の力を発揮しながら、ぜひ全国大会の雰囲気を楽しんできてもらいたいと思います。
いろいろな提案がありました~富川高校学習成果発表会~
令和6年2月19日(月曜日)
富川高校では各学年ごとに目標を決めてそれぞれの成果を発表する学習成果発表会が行われていますが、今年も地域探求・インターンシップ体験・進路決定までの道程など、さまざまな発表がありました。
地域探求では、「日高町での暮らしの充実」と題して、行事があまりなくなる冬期間に新たなイベントを開催してはどうかというものがありました。確かに冬に限らずここ最近はイベント的な行事が少ない状況で、日高町のイベントといえば、最大のものは「ししゃも祭り」ですが、コロナ禍や祭りの題材であるししゃもの記録的な不漁により4年間開催されていません。こうしたこともあっての提案だったかもしれませんが、発表したグループには、ぜひ具体的な企画書を作ってほしいと頼んできましたので、出来上がるのを楽しみにしています。
もう一つの地域探求は、「ヨーグルッペアイスで町おこし」というもので、町内の日高乳業で製造されている「ヨーグルッペ」という乳酸菌飲料(確か札幌のどさんこプラザにも置いてある結構有名なものです)をアイスにしてしまおうという企画で、実際に自分たちでアイスを作ってみたところ、おいしかったとの報告もありました。これも日高乳業に製品化できるか聞いてみる価値があるなあと思いながら発表を聞いていました。
インターンシップの体験では、自衛隊札幌地方協力本部静内分駐所と王子フォレストリー株式会社(木材会社)での職場体験が発表されていましたが、これまで経験はもちろんのこと、知識としても全く持っていなかった世界に触れて、2人とも貴重な経験となったようです。将来の進路にも考えたいと言っていましたが、果たしてどうなるのでしょう。
進路決定までの道程では、進学・就職それぞれの希望を実現するまでの取り組みが発表されていましたが、自分の目標に向かってなすべきことをしっかりと整理して着実に実行してきたことが伝わり、感心しました。後輩の皆さんにも大いに参考になったのではないでしょうか。
日高山脈襟裳国定公園の国立公園化に向けた取り組みに関する発表もありました。このテーマは、以前に国立公園化のシンポジウムが開かれたときに、出席していた富川高校の生徒さんにキャンペーン方法などを考えてと言っていたこともあるのですが、今回の提案も含めて町でもしっかり取り組んでいかなければなりません。
最後に紹介するのは、以前にも取り上げましたが、富川高校2年生の6人が山間部の小規模な水供給システムである共同水道の水質分析や管路図デジタル化(GIS)に取り組み、昨年、第25回日本水大賞厚生労働大臣賞を受賞、今回はその成果品である管路図を学習成果発表会のなかで受け取りました。さっそく共同水道の管理を担当している部署で活用させてもらいます。また、この活動がきっかけとなり、「OECD Project∞」という外国との交流活動にも参加した経緯が発表されましたが、一つの取り組みからさらなる世界が広がっていくことは素晴らしいことだと思いました。
プロの世界に挑戦
令和6年1月23日(火曜日)
二十歳を祝う会に参加した皆さんには、ぜひそれぞれの夢の実現に向かって歩んでほしいと会場で話しましたが、今回の二十歳を祝う会には大きな夢を抱いている参加者がいて、式典前に挨拶に来てくれました。その人は川越亮輔君、現在、岐阜県瑞浪市にある日本プロスポーツ学校2年生で、その夢というのはプロ野球選手になることです。

川越君は日高中学校在学中から苫小牧の硬式野球チームに所属、高校は野球強豪校の北海道栄高に進学し、4番一塁手で活躍しました。惜しくも甲子園出場はかなわなかったのですが、3季連続で全道大会に出場し、札幌円山球場でホームランを打ったこともあります。現在在学している日本プロスポーツ学校は、2年制の野球に特化した学校で、学校の野球チームは独立リーグ傘下の球団との交流試合のほか、都市対抗野球にも参加できるとのことで、川越君は、プロ野球選手になるためのステップとして進学したとのことです。

そして夢実現のための第1歩は、独立リーグ球団への入団で、4球団で構成されている九州アジアリーグの宮崎サンシャインズのトライアウトに挑戦し、狭き門のなか見事合格しチームの一員となりました。2月にキャンプイン、3月中旬からはいよいよリーグ開幕ですが、リーグ戦以外にも福岡ソフトバンクホークスの3軍、4軍との交流戦もあるとのことで、こうした経験を積んで、2年以内にプロ野球のドラフト指名を受けられるようになりたいと明確な目標を語っていました。ぜひ大きな夢を実現してほしいですね。
マスクなしでの再会~二十歳を祝う会~
令和6年1月22日(月曜日)
これまでコロナ禍でも二十歳を祝う会(令和4年までは成人式)は続けていましたが、マスク着用、検温、手指消毒、会話は控えめになどと、何かと制約の多い行事となっていました。昨年、コロナウイルスの感染症分類が5類になったことから今回はマスクの着用などは自己判断ということにしました。
というわけで、会場はここ数年と比べると式典が始まる前にあちこちで会話が弾んでいましたが、やはりコロナ禍の時のようにシーンとしているより、久し振りの再会を喜び合う賑やかな会場のほうがいいですね。これまで中止していた記念事業としての郷土芸能公演も復活して、今年は門別獅子舞保存会の皆さんによる獅子舞が披露されました。また、全員での記念撮影後も例年会場のあちこちで撮影をすることが多かったので、今年は会場の外にも撮影スポットを設けましたが好評でした。

二十歳を迎えた皆さんは、これからの長い人生、山あり谷ありでしょうが、いつの時にも胸に抱いている夢は決して忘れないで力強く歩んでほしいですね
4年ぶりの開催~日高消防出初式~
令和6年1月15日(月曜日)
今年は元日そうそう能登半島で大地震が発生し、家屋の倒壊、火災のほか津波の襲来があり、能登半島各地で甚大な被害となりました。被災地では多くの方が厳しい避難生活を送っており、心からお見舞い申し上げますとともに、1日も早く落ち着いた状況になることを願うばかりです。日高町でも2次避難のための住居の提供や人的な支援を行ってまいります。
こうしたように落ち着かない年の始めとなりましたが、コロナ禍で見合わせていた日高消防出初式が1月4日、4年ぶりに開催されました。当日は天候にも恵まれ、町内外からの来賓にご臨席いただきながら、屋外での消防職団員・消防車両による分列行進に始まり、屋内でも永年勤続者の表彰式などを行いましたが、消防関係者が一堂に会することにより、頼もしい日高消防の消防力を確認しました。

常日頃は、火災や救急への対応が業務の中心となる消防ですが、いざ災害となれば住民からの期待に応える一番身近な存在となりますので、日常の訓練などを通して一層精強な組織となるよう努めていきたいと思います。
皆さんとてもお元気
令和5年9月28日(木曜日)
日高町では、毎年100歳になられた方にそれぞれの誕生月にお祝いを差し上げていますが、9月には総理大臣からもお祝い状と記念品が届きます。先日、このお祝いをお届けにおじゃましましたが、今年はなんと8名もいらっしゃいました。ご長寿の方がたくさんおられるというのは大変うれしいことですね。
今年度100歳になられる方は、大正12年、13年生まれの方ですが、大正12年といえば関東大震災が起きた年で、今月は大震災後100年との報道も多々ありました。ちなみに大震災が発生した9月1日は、フランク・ロイド・ライトが設計した帝国ホテル新館の開館式の日で、祝宴の準備中に地震が起きたとのことですが、建物は無傷だったそうです。
町と国のお祝いで2回うかがった折りにいろいろとお話をするのですが、皆さんとてもお元気で、昔話を聞かせていただいたり日頃の過ごし方など話してくれたりします。中には今でも一人でバスに乗って札幌にパチンコに行くという方もいるから驚きです。
1世紀も生きてこられて、こんなにお元気でおられることに尊敬の念を抱かずにはいられません。これからも変わらずに楽しい日々を過ごされることを心から願っています。

雄大な日高山脈の麓でツーデイズエンデューロ
令和5年9月25日(月曜日)
9月16日、17日に町内日高地区で「2023日高ツーデイズエンデューロ」が開催されました。エンデューロという競技はあまり馴染みがないかもしれませんが、1984年に北海道で初めて2日間のエンデューロ競技会が苫小牧市で開催され、その後1986年からは日高町で行われるようになったそうです。最近はコロナ禍もあり、今年は4年ぶりの開催となりましたが、参加者は約230名とのことで、海外からも、カナダ・オーストラリア・イギリスから6名の選手の参加がありました。
私は、競技大会前日の開会式に出席しましたが、高原荘(町営の温泉宿)前の広い駐車場が各参加チームのバイクが並べられたテントで埋め尽くされていました。日高ツーデイズエンデューロでは一般公道も走るため、競技前の検査では、ナンバープレートや保険加入の確認、さらに保安部品の機能や排気音量も厳しくチェックされるそうです。

日高町でのコースの特徴は、1周のコースが130kmを超えるほど長いこと、大半は未舗装路となっているが、一部に国道などの一般道路があること(当然法定速度内で走行しなければならない)、未舗装路も林道・作業道、草原や河原、川渡り、獣道や笹藪を刈り拡げただけの道、さらに全く整備していない完全なオフロードなど、ありとあらゆるシチュエーションがあることです。海外からの選手の中には、「日高は次々にいろいろな道、路面、景色が展開するので、めまぐるしく変化する状況に、瞬間瞬間で対応しなければならず、でもそれがエンデューロライダーとしてたまらない魅力なんです」と話してくれた方もいました。まさに日高山脈の麓で、雄大な自然を存分に味わいながらの競技会となったと思います。
【エンデューロ】
オートバイなどで行われるオフロードの耐久レースの一種。数十km、時には100kmを超える長距離のコースで競われ、コース距離が長く、路面がバラエティに富んでいるのがモトクロスとの一番の違い。モトクロスはコースが人の手によって作られているのに対し、エンデューロは基本的に自然の地形を活かした、あまり人の手が加わっていないコースが多い。
日高ツーデイズエンデューロでは、閉鎖されたコースではなく、一般道路も走行して、タイムチェックポイントを指定された時間内で走りながら、4カ所に設けられたスペシャルテスト(タイム計測区間)でスピードを競う。
富川小学校が開校150周年
令和5年9月22日(金曜日)
9月15日、富川小学校で開校150周年の記念式典が行われました。同校は、明治6年、開拓に入っていた仙台藩の官舎を利用した佐留太教育所として発足し、その後、佐留太小学校、佐留太尋常高等小学校、富川尋常高等小学校という改称を経て、現在の富川小学校となりました。合併前の旧門別町(平成18年に旧門別町と旧日高町が合併して現在の日高町が誕生しました。)が、明治5年の開拓使浦河支庁沙流出張所の設置を開基としていますので、その翌年に創立された富川小学校は、ほぼ町と同様の歴史を歩んできたといえます。
明治6年というのは、どんな年であったのだろうと調べてみると、下記のような歴史を感じる出来事がありました。
・学制に基づいた日本で最初の小学校(東京師範学校附属小学校)が誕生
・郵便料金が全国均一となる(書状は市内1銭、市外2銭)
・石高制を廃止し、一律の田畑反別課税制とする
・朝鮮使節派遣の中止が決定し征韓論派が敗れ西郷隆盛・板垣退助らが参議を辞職する(明治6年の政変)
150年という歴史は本当に長いもので、歴代の校長をはじめ教職員の皆さん、そして富川小学校を支えてきたPTAや地域の皆さんのご尽力に心から感謝です。
記念式典では、5年生、6年生の合唱が披露されたほか、アンサンブルグループ奏楽(そら)の皆さんの演奏が花を添えてくれました。
午後からは、残念ながら私は参加できなかったのですが、戦場カメラマンの渡部陽一さんと元スピードスケート日本代表で金メダリストの高木菜那さんの記念講演が会場を総合町民センターに移して開催されました。
150周年を迎え、同時に新たなスタートとして、児童のみんなには元気に学び、遊び、楽しい小学校生活を送ってほしいと改めて思う1日でした。
地域の水は自分たちで守る~地域ぐるみの水道維持管理支援の取り組み~
令和5年7月14日(金曜日)
去る6月13日、第25回日本水大賞・2023日本ストックホルム青少年水大賞の表彰式・受賞活動発表会が、東京都の日本未来科学館で開催され、富川高校が富良野高校・北海道立総合研究機構(道総研)・白石航希さんとともに厚生労働大臣賞を受賞しました。

【受賞の皆さん】
富川高校 石田涼空さん、大倉隼翔さん、柏木花音さん、高木涼馬さん、山口寿乃さん、ウィリアム・ヴェレンズエラさん(50音順)
北海道立総合研究機構(地域研究部 牛島 健 研究主幹)
白石航希さん(元日高町職員))
日本水大賞は、安全な水・きれいな水・おいしい水にあふれる21世紀の日本と地球を目指し、水循環の健全化に役立てる水防災・水資源・水環境の分野における様々な活動を対象に、社会的貢献度が高い特に優れたものを表彰し、広く国民に発信することを目的として、平成10年に創設されたものです。
上水道、簡易水道とは違い、地域住民の皆さんが自分たちで管理している小規模な水供給システムである「地域自立管理型水道」(普段は、共同井戸・共同水道という名称を使っています)については、道総研が北海道の状況として、管路がどこに埋まっているのかなどの施設情報が、記憶やメモ頼りできちんと整理されたものがないこと、定期的な水質検査が行われていない場合もあるなどの問題を確認していたそうで、このような問題は日高町でも同様でした。
富川高校がこの活動に取り組むことになったきっかけは、2017年から道総研が地元の高校と連携して「地域自立管理型水道」の管理体制づくりを行っていたことを知った元日高町職員の白石航希さんが、昨年、道総研に連絡して富川高校に繋いだことだったそうです。富川高校の理解、水道利用組合の協力、白石さんや当町の水道部門のサポートなどがあり、「総合的な探究の時間」の授業の中で、当時2年生の6人により活動がスタートしました。
具体的な活動は、水質分析、管路図デジタル化(GIS)、その成果発表ですが、特に管路図のデジタル化は今まで全くの手付かずだったので、今後の施設の維持管理に大いに役立つものです。


こうした活動結果は、富川高校の学習成果発表会で学内外に発表されたとのことですが、高校生の皆さんは、自分たちが地域にとっての戦力として大きな役割を果たしたことを強く感じていると思います。今年度も活動を継続するほか、Youtubeで活動の様子を英語で発信するとのことで、ただいま動画を作成中とのことでした。(途中経過を見ましたが中々の出来映え)
富川高校の「総合的な探究の時間」では、私も以前に2年生の地域探求で、まちづくりというテーマで話をさせてもらったことがありましたが、それを受けていろいろな意見がありました。これからも是非、自分たちで考え、そして行動するという探求活動を通じて、地域に発信を続けてもらいたいと思います。
日高産ワイン誕生
令和5年5月30日(火曜日)
去る5月13日、道の駅樹海ロード日高でワインの試飲会が開かれました。提供されたワインは、町内富岡の馬場幸一さんが栽培した2022年産のブドウで醸造された赤ワインで、「defi 88 ans(デフィ 88 アン)」と名付けられていましたが、これはフランス語で「88歳の挑戦」という意味です。

馬場さんが栽培していたブドウは「山幸(やまさち)」という品種ですが、「清見(きよみ)」というブドウ品種と北海道内に自生する「山ブドウ」と掛け合わせた野趣あふれる香りと力強い酸味が特徴の耐寒品種だそうで、十勝管内池田町で開発されたものと聞きました。
馬場さんは、2018年からブドウの栽培を始めて、地域おこし協力隊の三浦翔さんの協力も得ながら徐々に苗木を増やし、昨年の秋に念願のワイン造りが開始され今年2月に86本のワインが完成し試飲会の開催となりました。
ワイン醸造は、帯広市のワイナリー「あいざわ農園」に委託して行われ、当日は、相沢一郎代表も会場を訪れて皆さんとワイン談義に花を咲かせていました。今回のワインの特徴としては、比較的熟成期間が短いためアルコール度数もやや低い(10.5%)とのことで、個人的な味の感想は、軽い口当たりでとても飲みやすいと思いました。(けっこうグイグイいけます。)

馬場さんは、これからもブドウの苗木を増やしてゆくゆくはワイナリーも、と夢を語っておられました。89歳の挑戦はまだまだ続きます。
ホッカイドウ競馬スペシャルナイター
令和5年6月1日(木曜日)
5月16日、今年オープンした北海道日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールドHOKKAIDO 日本ハム-西武戦で、ホッカイドウ競馬のPRイベントが行われました。これは競馬を運営する北海道軽種馬振興公社による協賛試合として「ホッカイドウ競馬スペシャルナイター」と銘打って開催されました。

当日の始球式は、昨年のリーディングジョッキーの落合玄太騎手と、今年のホッカイドウ競馬アンバサダーの元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士さんが競馬の勝負服姿で現れ歓声を受けていました。このほかに球場内で特設ブースを設けて、門別競馬場でのレース中の騎手の目線を体験できるVRコーナーやクリアファイルにレーシングガイドなどを入れて1万枚配布したほか、場内の大型ビジョンでのPR映像など、来場者にホッカイドウ競馬をアピールした1日でした。これがきっかけで、今まであまり関心がなかった方にもホッカイドウ競馬・門別競馬場に興味を持ってもらえたらと思います。


ちなみに、試合の方は日本ハムが新庄監督プロデュースの赤と黒の派手なユニフォームを着用しての戦いでしたが、1点リードしていた9回表、2アウトランナーなしから同点ホームランを浴びて延長戦に突入、延長12回約4時間半の長い戦いの末、残念ながら2-4で日本ハムが敗れました。